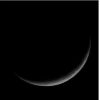毎日、酷暑が続いております。
地球は今までに4回、変化しているというデータがあります。
氷河期が地層を見たら4回来ていて、1万年前の地層からは、電波探知機が、見つかったとか。
今のような文明がすでにあって、氷河期になり、そこからまたゼロに戻って、また今に至ってるのかもしれませんね。
世界的に天候の異変が起こっているようです。
さて、ピンと来ませんが、今日から立秋です。
立秋は、暦便覧には
初めて秋の気 立つがゆへなれば也
このように記されていて、「初めて秋の気配が感じられる季節」という意味があります。
暦便覧とは、江戸時代に「著者 太玄斎」によって記された暦の解説書
暦を見る上で『二十四節気』と呼ばれる、「1年を24つに区切って季節を分けた考え方」があり、その中で立秋は「13番目」にあたります。
でも、8月にある立秋のことを「秋が始まる日」と言われても、かなりの違和感があります。
また、この立秋から立冬の間を秋と言われても、8月や9月はまだまだ暑い時期が続きます。
これらの日本の暦は中国による影響が大きいのですが、この立秋をはじめ立春や立夏、立冬など、日本の四季にも大きく影響をしている暦は、
古代中国の「黄河流域の寒い地域」で作られたものです。
だから、日本とは「季節感のズレ」が生まれてしまい、8月から秋が始まるというような立秋が誕生したと考えられています。
この立秋とは「秋の始まり」を意味する暦なので、四季を大切にする私たち日本人にとっても、非常に大切な暦だということがわかります。
この二十四節気では、立秋はとても重要なポジションを占めています。
それは他の暦との兼ね合いも含めて見ると、
「立春」から「立夏」までを春
「立夏」から「立秋」までを夏
「立秋」から「立冬」までを秋
「立冬」から「立春」までを冬
暦の上ではこのように定めています。
今回のテーマである立秋を加えて
立春・立夏・立秋・立冬
これを「四立」と呼んでいます。
さらに「二至二分」を加え
二至:夏至・冬至
二分:春分・秋分
四立:立春・立夏・立秋・立冬
この8つを「八節」と呼びます。
この8つは、日本でも季節を語る上でかなり重要な暦です。
どれもその時期になると話題に上ることばかりです。
春分や秋分は祝日にもなってますし、夏至や冬至も行事があって楽しみな日となっています。
日本ではこの八節がいつかを覚えておくと、いろんなつながりがあって面白いです。
以前の日本では旧暦で日付が動いていました。
その旧暦は月の満ち欠けで、ひと月の長さを決めていました。
ただ旧暦ではズレが大きく、1年が13ヶ月になる閏月を入れたりするなど大きな調整が必要でした。
だから数年前と月日は同じでも季節感が違ったりしたので、
「○月○日だからそろそろ田植えをする」
みたいな目安にはなりませんでした。
そこで農業などで季節を知ることは欠かせないので、季節を知るための「二十四節気」が使われるようになり、季節を表す言葉として浸透したのです。
でも、明治になって「旧暦」から「新暦」に変更した時に、旧暦と新暦はもともと平均1ヶ月ほどのズレがあるにもかかわらず、「旧暦」の日付をそのまま現在の日付に移してしまったため、今のように季節感のズレが生まれてしまったのです。
だから8月ですごく暑いのに立秋を迎えたから、「暦の上では秋」なんていう言い方になってしまうのです。
二十四節気をさらに約5日おきに分けて、気象の動きや動植物の変化を表したものを「七十二候(しちじゅうにこう)」と言います。
今では見なくなったものも多いですが、この七十二候によって立秋はどんな季節として迎えているのかがイメージしやすくなってきます。
初候(8月7日頃)
涼風至(すずかぜいたる)
涼しい風が吹き始める頃を言います。
次候(8月12日頃)
寒蝉鳴(ひぐらしなく)
蝉のひぐらしが鳴き始める頃を言います。
末候(8月17日頃)
蒙霧升降(ふかききりまとう)
まとうように深い霧が立ち込める頃を言います。
時候の挨拶に「立秋の候」という言葉がありますね。
漢語調の書き出しの挨拶の時に使われますが、立秋の候という事で
秋が始まる季節となりました。
といったような意味になります。
立秋の日にちや期間も説明してきましたが、日にちは8月7日か8日で期間として表す場合は、
「立秋(8月7日ごろ)」~「処暑(8月23日ごろ)」の前日までの期間
この約2週間の期間のことを『立秋』という場合もあります。
ですので、立秋の候という時候の挨拶を使うのならこの期間になります。
立秋の候の使い方や例文
この立秋の候を使った書き出しの挨拶文はどのようになるのか。
その使い方と例文をいくつか紹介したいと思います。
立秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
立秋の候、まだまだ厳しい暑さが残る季節です。
立秋の候、記録的な暑さが続いておりますが皆様お元気でいらっしゃいますか。
このような感じです。
とは言え、この時期は残暑見舞いの季節になります。
立秋の候という使い方よりも、「残暑お見舞い申し上げます。」という使い方の方が一般的です。
立秋と残暑見舞いの関係
この立秋(8月7日ごろ)からは、暦の上では「秋」となります。
ですので、この時期に出されるお手紙に「暑中見舞い」がありますが、この立秋を過ぎてからは「残暑見舞い」になるのですね。
こんなふうに感じてしまうので、ついうっかり暑中見舞いとして出す方もいるかもしれません。
でも暦の上では秋なので、もうすでに夏は過ぎています。
ですので、暑中見舞いと残暑見舞いの時期は、マナーとして覚えておくようにしましょう。
暑中見舞いの時期
小暑(7月7日ごろ)~立秋(8月7日ごろ)の前日まで
残暑見舞いの時期
立秋(8月7日ごろ)~白露(9月8日ごろ)の前日まで
ただし、9月になると区切りが悪いため
「8月いっぱいまでに届く」ようにすることがマナーとなっています。
この立秋を迎える8月ですが、そんな時期に旬を迎える食べ物にはどんなものがあるのか。
ここでいくつかまとめましたので、まずはご覧ください。
【野菜】
ししとう、えだまめ、かぼちゃ
とうもろこし、トマト、なす、ピーマン
にがうり(ゴーヤ)
【果物】
パイナップル、梨、もも、ぶどう
マスカット、すだち
【魚貝類】
いわし、かんぱち、あなご、あゆ、ウニ
こんぶ、くるまえび
冬至にはかぼちゃを食べる風習がありますが、かぼちゃの旬は8月となっています。
季節は巡ります。
水分をしっかりとって乗り切っていきましょう!